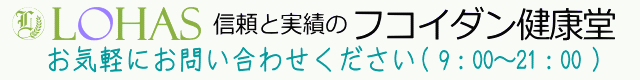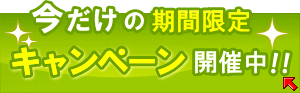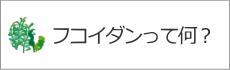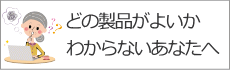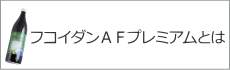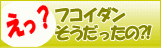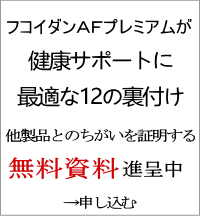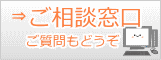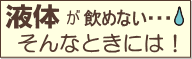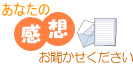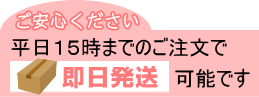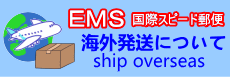「フコイダン」って何?
フコダインと間違う人も多いですが、正式名称は 「フコイダン」
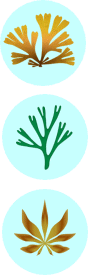
テレビでもとりあげられるようになって知られてきましたが、まだまだ「フコイダン」を知らない方も多いかもしれませんね。
フコダイン・フコインダン・フコイダイン・フコダンなど、まちがって呼ばれたり、覚えられていることもよくありますが、正しい成分名はフコイダン(fucoidan)です。
じつは、「フコイダン」は、あなたの身近に存在しているものなんです。
もずくやワカメ、こんぶなどをさわったときや、食べるときヌルッとしますよね?
あのヌルヌル成分にふくまれているのが「フコイダン」です。
このもずくやワカメ、こんぶは海の中でくねくね・ゆらゆらしながら育っています。
これは、海の中の激しい潮のながれから身をまもるため。
くねくね・ゆらゆらできるのも「フコイダン」ヌルヌル成分のおかげなんです。
また、ヌルヌル成分でバリアーをはって、微生物から自分自身を守ったり、乾燥から身を守るはたらきもしています。
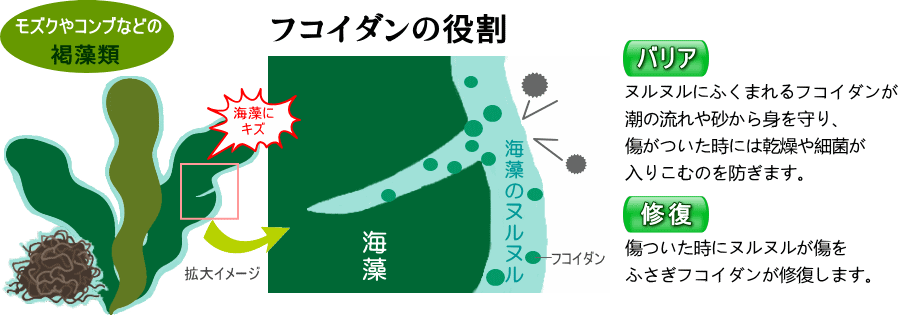
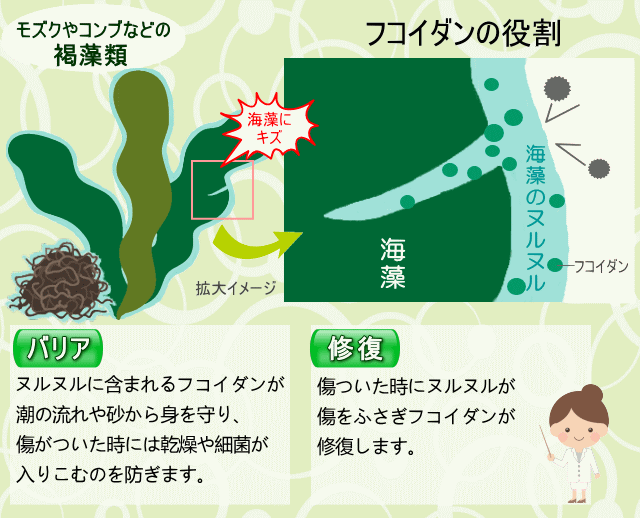
さて、このフコイダン、
じつは同じようにくねくね・ゆらゆらしているコンブやモズクといった海藻類の中でも種類によってふくまれている量がちがいます。
メカブやコンブよりも、モズクは3~4倍フコイダンをふくむ量が多くなります。
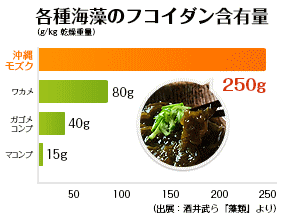
これにもきちんと理由があります。
それは、メカブやコンブよりもモズクが浅い海に生きているからなんです。
海で、引き潮の時間になると、モズクは直接太陽の光を浴び、乾燥してしまいます。
乾燥から身を守る役目をするのがフコイダンだというのは先ほどお話したとおりですね。
だから、浅い海に住むモズクには、自分を守るためにも他のワカメやコンブといった海藻類よりもフコイダンが多くふくまれているのです。
もっと専門的に・・フコイダンを構成しているのは
フコイダンは多糖類
フコイダンは、糖(とう)同士が分子レベルの小さな状態でくっついている多糖体(たとうたい)といわれる形をしています。
糖ってなに??
糖といえば、あまい砂糖を思いかべませんか?
ここでいう、糖の体の中でのはたらきは、「グリコーゲン」となって人間のエネルギー源になる、ということ。
またタンパク質とくらべると、肥満を連想し、脂質と共に悪玉扱いされることも多いですね。
しかし、糖の役割はそれだけではありません。
からだの中でタンパク質などと結びついて糖鎖の形になり、血液型を決定したり、免疫反応、生体情報のアンテナになるなど、一口に言って生命現象のカギとも言える重要な役割をもっているのです!
「糖」は、糖質工学・糖鎖工学として医薬・食品・その他工業的な利用や研究にもつかわれています。
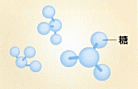
図をかくと、右図のようなこんなかんじですね
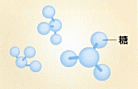
このちいさなまるいものが、糖といわれるもの(イメージ)です。
フコース、ガラクトース、マンノース、キシロースという糖などです。
これらが鎖でつながれたようにくっついています。
このくっついたものに、さらに硫酸基(りゅうさんき)やウロン酸が結びついたものを「フコイダン」といいます。
え!?硫酸が入ってるの?危険じゃないの?
フコイダンがもつ大切な構成成分・硫酸基(りゅうさんき)。
硫酸といえば、理科の実験でもおなじみではないでしょうか?
ごぞんじのとおり、劇薬でしられている硫酸の元になっている成分なのですが、単体で存在するときは硫酸基(りゅうさんき)といって、まったく無害なものなんです。
硫酸基の特徴は、水分を保ち、ヌルヌル状態をつくり出すこと。
そして、じつはこの硫酸基、人間の胃にもあって、粘膜の粘質性の源になっているのです。
フコイダンは、この硫酸基をもつことで、ヌルヌル感をだして、人間の粘膜となじみやすくすることができたのです。