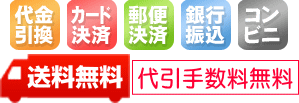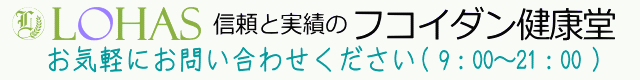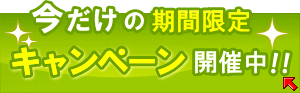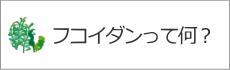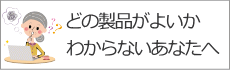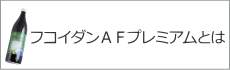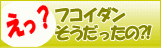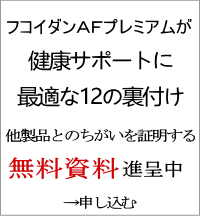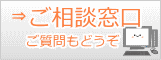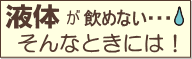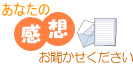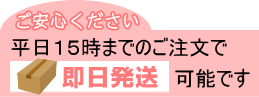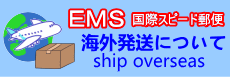海藻の種類でのちがいは何?
モズク・ワカメ・昆布、いろいろあるけれど
フコイダン(fucoidan)は、硫酸化多糖の一種で、コンブやワカメ(メカブをふくむ)、モズクなど褐藻類のネバネバ成分(粘質物)に多くふくまれています。
海藻の種類によってなにかちがうのでしょうか?
と疑問に思われご質問をいただくこともございます。
ここではモズクから抽出されたフコイダンが、その他の海藻とどう違ってくるのかについてお話します。
それぞれの海藻の特徴
良質なフコイダンを効率的に抽出できる海藻はどれ?
フコイダンは褐藻類(褐色の海藻)のほとんどにふくまれています。
モズク・ワカメ(メカブ)・コンブ・ヒジキなどが褐藻類です。
それぞれの海藻によって特徴があり、
たとえば、コンブにふくまれる多糖類にはアルギン酸(ヌメリ成分)の含有量が多く、フコイダンを精製するには工程が複雑で、時間と手間がかかります。
オキナワモズクはその逆で、アルギン酸の含有量が少ないので、純度の高いフコイダンを効率的に抽出することができます。
またメカブについては、北海道から九州までの日本海沿岸や、太平洋沿岸、瀬戸内海沿岸や朝鮮半島でとれるワカメのメカブは粘性が高く、モズクの次にフコイダンの含有量が多くなっています。
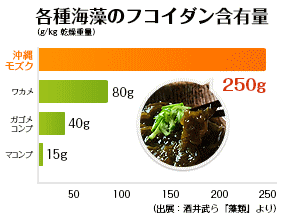
モズクにふくまれるフコイダンの量
フコイダンの含有量がとくに多い海藻はモズクです。
40グラムのモズクには、約1008ミリグラム(約1グラム)もの フコイダンがふくまれているといいます。
モズクにもさまざまな種類がありますが、中でもフコイダンが多くふくまれるのは「フトモズク」という種類です。ふつうのモズクより形状が太いのが特徴ですが、なかでもオキナワモズクと呼ばれる種類にフコイダンが多くふくまれます。
オキナワモズクの特徴は、純度が高く、製造工程がきわめて簡単でフコイダンを抽出しやすいということです。
フコイダンを効率よく精製するには、オキナワモズクが一番適していることがわかり、フコイダンを安定して供給することが可能となっています。
海藻によってちがうフコイダンの構造
フコイダンの構造式
フコイダンが、1913年スウェーデンのウプサラ大学のキリン教授によって発見されてから90年以上の間、その化学的な構造は推定されてはいましたが、確定的に決定されたのは発見されてから83年後の1996年です。
この間、多くの研究者たちにより化学構造をふくむ理化学的性状などが研究されてきました。
1996年になって、初めてガゴメコンブからのフコイダンの化学構造や生理活性についてもあきらかにされました。ガゴメ由来のフコイダンだけでも3種類の化学構造が明らかになり、それぞれF-フコイダン、Uーフコイダン、G-フコイダンがあります。
オキナワモズク由来のフコイダンはそれとは異なる化学構造をしています。
フコイダンは、糖がたくさん結合した多糖類の一種でコンブにもふくまれていますが、コンブは、もう一つの多糖類であるアルギン酸の含有量のほうが圧倒的に多く、フコイダンはそれほど多くふくまれていません。
一方で、オキナワモズクは、そこにふくまれる多糖類の9割をフコイダンが占めています。
オキナワモズク由来フコイダン
高分子と低分子
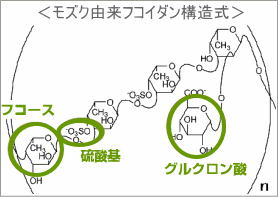
こちらはモズク由来の構造式です。
フコースを主成分として、硫酸基・グルクロン酸が結合した状態(高分子)でフコイダン本来のパワーを発揮することができます。
たとえフコイダンを小さくしても、腸から吸収されるまでに、その性質上ふたたびくっついて(凝集されて)しまって大きくなることもあり、せっかく小さくしても意味がなくなってしまいます。
また「低分子フコイダンは吸収率がよいので有効だといいう研究者もいるが、低分子化によって硫酸基がバラバラになると、フコイダン本来の活性が失われる可能性を否定できない」というような研究者の声もあがっています。
このことから、弊社では従来品を改良する際に、「高分子フコイダン」を採用いたしました。実際、研究発表されているフコイダンのそのほとんどは「高分子」です。
高分子ということで体にに吸収されないというわけではありません。体に吸収されることが最近の研究で明らかになってきていて、研究結果で吸収に関するよい結果が確認されている質の良いものがあります。